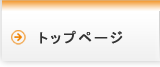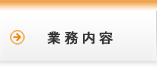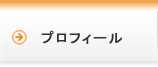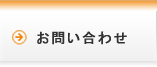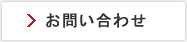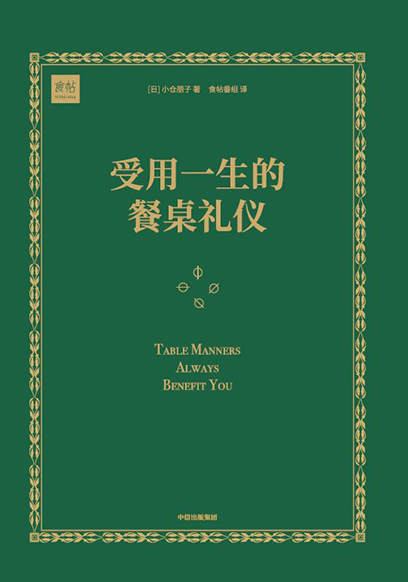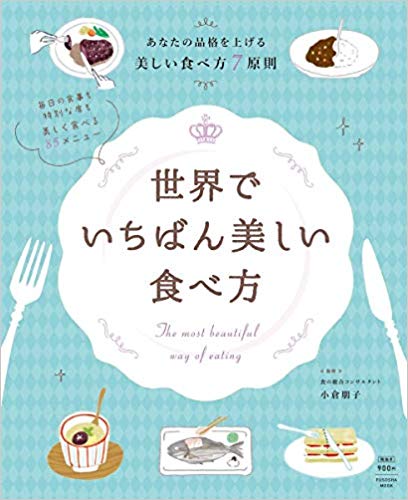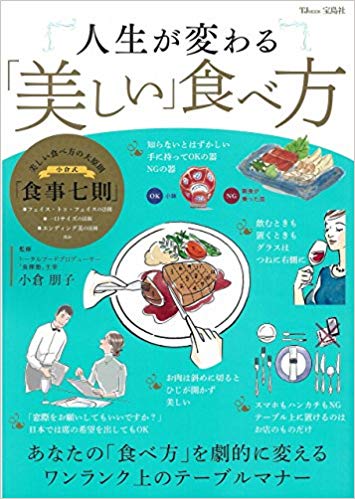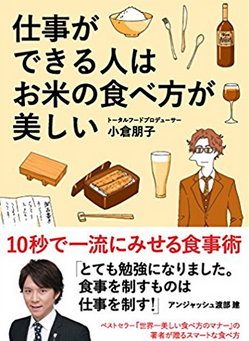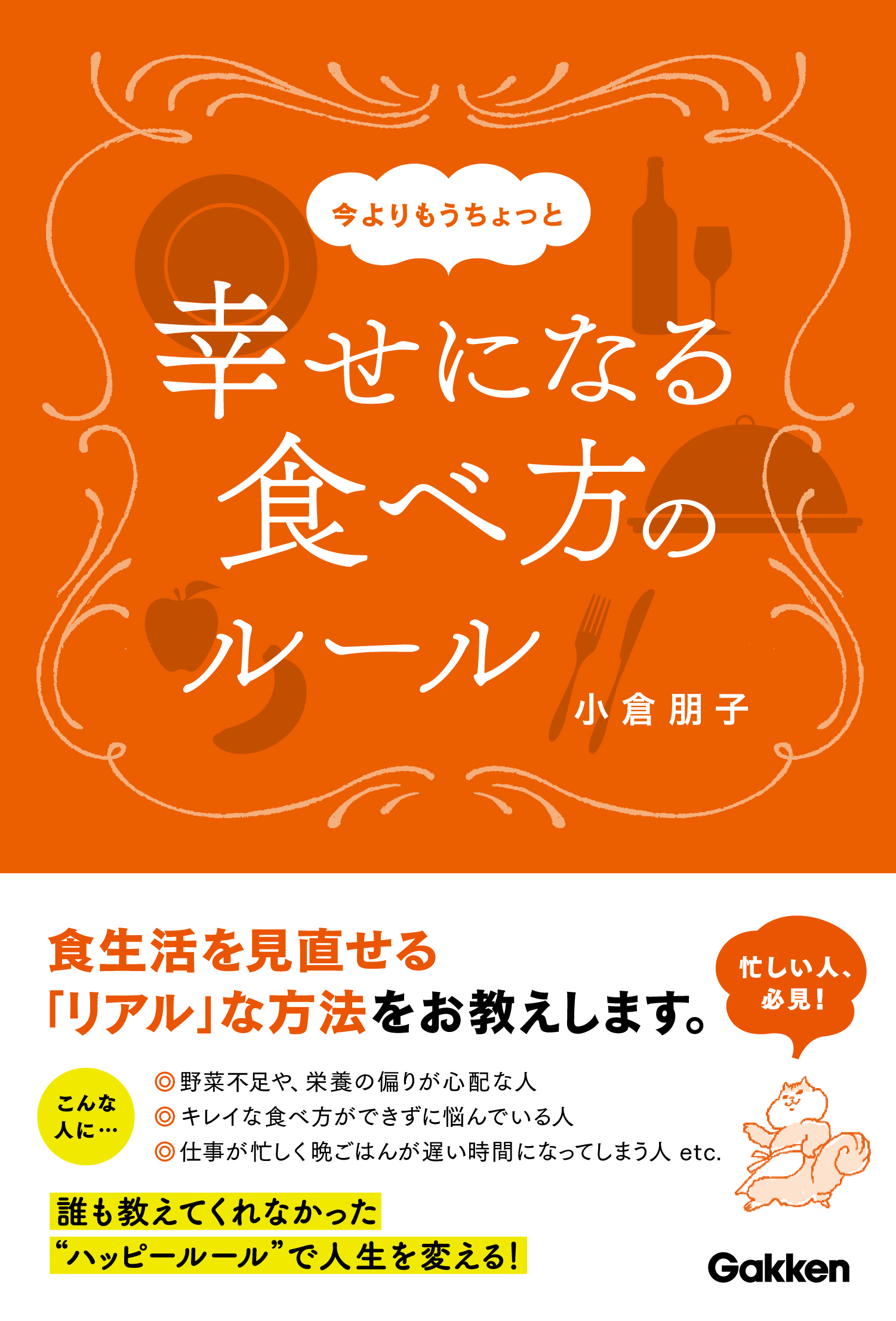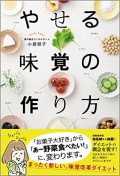| 2025年12月18日 | Nスタ コメント出演します |
|---|---|
| 2025年11月16日 | ちょっとバカりハカってみた監修しました |
| 2025年11月09日 | Nスタ コメント出演します |
| 2025年09月20日 | テレビ出演お知らせ~クイズX年後の当たり前 |
| 2025年08月26日 | [おいしい」についての授業しました |
トップページ > 小倉朋子の専門分野コラム一覧 > メンタルと食 > 食品偽表示
食品偽表示
2013年11月13日
日本酒も出たので、さらに日本酒は出るかもしれませんね。
メニュー表記偽表示の問題が、外食全般に広がってきました。
今月の食輝塾のセカンド授業で、今回の問題と今後、その理由や背景は何か、
私たち消費者ができること、できないことなど、お話しています。
日本の法律は一律になっていないため、消費者が購入時に
出所を100%わかる術は現在のところありません。
今後は法律が変わる申請を出していますが、
現在のところ、外食は表示義務ないのです。
それは、わからなかったら店の人に聞けばよい
という前提のもと。
しかし現代の飲食の世界では、もはやその理由は陳腐。
表示のモラル規範の中には、時代が変わり、客の意識も変わり、アレルギーなど
様々な肉体に及ぼす問題も増えている現状を、企業も勉強して対応しないといけないですよね。
ただ、消費者も課題多し。
食材からの調理をし、実際に多々口にした経験があればわかることもあります。
企業依存して満足しないように、全体的に見直しの時期に日本は過渡期に来ていますね。
というか、もっと前からですが…。
ちと遅いですね。
私はオタクなので、日ごろから分解して食べたり、いろいろアンテナを細かくやって
食べていて、比較対象を自らの中に作って沢山ストックしている(体に)ので、
大丈夫だと自信あります。
それは、自身が納得いくものを食べられる、という自信なの。
人間は比較対象があって初めて評価基準を設けることができます。
その比較は、自身の中にあり!と思います。